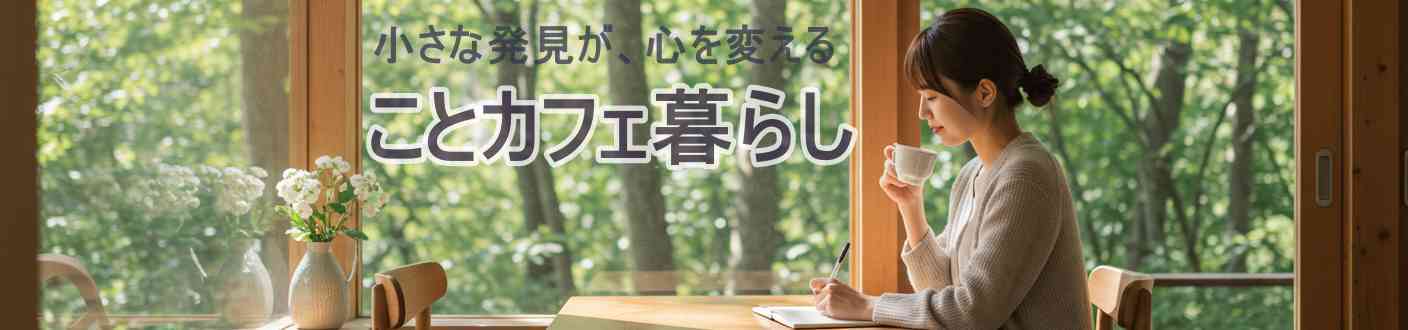「おろし金が見当たらない!」そんなときでも、実はあわてる必要はありません。身の回りのキッチン用品を少し工夫すれば、大根おろしもとろろも、ちゃんと作れるんです。
料理の途中で「あっ、ない!」と焦った経験がある方も多いはず。でも大丈夫。おろす動作の“代わり”になる仕組みを知っておけば、すりおろし器がなくても立派に代用できます。
この記事では、主婦目線で選んだ「家にあるもので代用できるおろし金アイテム10選」を、使い方や注意点付きでご紹介。
さらに、食材別のおすすめ代用テクや、安全に使うコツ、そして「やっぱり専用器がほしい人向け」のおすすめ商品までまとめています。
今日のごはんづくりにすぐ役立つ、暮らしの知恵がギュッと詰まった保存版です。
結論|おろし金は“家にあるモノ”で十分代用できる!

おろし金は「摩擦」や「押しつぶし」で食材を細かくする道具。つまり、同じ動きを再現できれば、他のもので十分代用可能です。
包丁・ピーラー・フォーク・ビニール袋など、家にあるものを使えば、見た目も味もほぼ同じような“おろし”を作ることができます。とくに大根や山芋、にんじんなどは、力加減さえ調整すれば、どの代用品でもきれいに仕上がります。
すりおろす目的が「香りを引き出す」「なめらかにする」「食感を柔らかくする」などであれば、それぞれの食材に合った代用法を選べばOK。
ポイントは“無理にすりおろそうとしない”こと。食材の特徴を活かしながら、ちょっとした発想転換でおいしい仕上がりが叶います。
おろし金の代用を選ぶポイント

代用品を選ぶときのコツは、食材の「硬さ」「水分量」「用途」に注目すること。
固い野菜(にんじん・りんごなど)は、削るタイプの代用品が向きます。
水分が多い野菜(大根・山芋など)は、押しつぶすタイプが使いやすいです。
また、すりおろし後の用途――例えば“とろろごはん用”か“薬味用”か――でも選び方は変わります。
衛生面を重視したいなら、ラップ越しにおろす、使い捨て袋を使うなどの工夫も◎。すりおろし器がないときは、「摩擦」と「圧力」をどう再現できるかがカギです。
摩擦の強さで選ぶ(繊維の多い野菜)
繊維が多い野菜には、ザルやしゃもじのような凹凸面が効果的。手軽に摩擦を作れます。特に大根やにんじん、れんこんのように硬くて繊維が多い野菜は、強い摩擦を与えることで細かくなり、食感が均一になります。
もしザルの網目が粗い場合は、角度を変えてこすることでよりスムーズにおろせます。
また、しゃもじや金属のスプーンの背を使うときは、滑らせる方向を一定に保つと効率的です。調理台の上に布巾を敷いて固定すると安定感もアップ。
摩擦が強い分、手指を擦りやすいので、滑り止め付きの手袋を使うと安心です。少し時間はかかりますが、その分だけ野菜の風味が立ち、シャキッとしたおろしが完成します。
清潔さで選ぶ(衛生面・ニオイ移り)
しょうがやにんにくなど匂いの強いものは、ラップの上からこすって使うのが便利です。ラップを一枚敷くだけで、器具や手に匂いが残りにくく、後片づけも簡単になります。
また、ラップを使うことで食材の衛生状態を保てるため、生ものを扱うときにも安心。使用後はラップを捨てるだけで済むので、時間のないときにも重宝します。
さらに、ニオイ移りを防ぎたい場合は、使い捨て手袋や食品用ポリ袋を併用するとより効果的です。器具を洗うときには、レモン汁や重曹を使うと匂いがスッキリ落ちます。
清潔さを意識した調理は、見た目だけでなく味や香りの仕上がりにも良い影響を与えてくれます。
手軽さで選ぶ(洗い物・時短重視)
包丁やピーラーなど、洗いやすい道具を選べば後片づけもラクになります。さらに、使う前に準備を整えておくことで効率もアップします。
まな板を固定して滑りにくくする、使う道具を近くにまとめておくなどの工夫で作業の無駄を減らせます。
例えば、ピーラーなら持ち手が太めのものを選ぶと長時間の使用でも手が疲れにくく、包丁は軽めのものを使えばスピーディーに刻めます。
また、すりおろし後の洗い物を減らすために、調理中にボウルや皿を使わず直接鍋に入れる方法もおすすめ。
作業の流れを意識することで、全体の時短効果が生まれます。日常のちょっとした工夫が、忙しい調理時間をぐっと快適にしてくれます。
おろし金の代わりに使える“家にあるモノ”10選

おろし金がなくても、キッチンを見渡せば代用品は意外とたくさんあります。
ビニール袋、ピーラー、しゃもじ、スプーン、フォークなど、どれも一工夫で“おろす動作”を再現可能。
ここでは、それぞれの使い方・向いている食材・注意点をまとめた一覧表をご紹介します。
スマホでも見やすく整理しているので、すぐに実践できます。
🍽 おろし金の代用アイテム一覧(スマホ対応版)
🍽 おろし金の代用アイテム一覧(スマホ対応版)
🥢 ビニール袋+麺棒
使い方: 食材を袋に入れて叩く or 押しつぶす
向いている食材: 山芋・大根・じゃがいも
注意点: 強く叩きすぎると袋が破れるので、二重にすると安心
🔪 包丁
使い方: みじん切りまたは包丁の背で叩く
向いている食材: 玉ねぎ・にんじん・りんご
注意点: 指を切らないように、端を押さえすぎない
🧴 ピーラー
使い方: 薄く削って重ね、刻んでおろし風に
向いている食材: にんじん・きゅうり・チーズ
注意点: 固い野菜は滑りやすいので、まな板を固定する
🍚 しゃもじ
使い方: 凸凹面で押しつぶすようにこする
向いている食材: 山芋・じゃがいも・大根
注意点: 熱湯消毒してから使うと衛生的
🧻 ラップの刃
使い方: ギザギザ部分に軽く押し当てておろす
向いている食材: にんにく・しょうが
注意点: 指先を切らないよう慎重に。小量向き
🍴 フォーク
使い方: 食材を押さえながらすり潰す
向いている食材: バナナ・アボカド・りんご
注意点: 力を入れすぎると滑るので、布巾を敷いて固定
🧺 おろし付きザル
使い方: ザルの目で軽くこする
向いている食材: 大根・にんじん・りんご
注意点: 力を入れすぎると割れることがあるので注意
🥄 スプーンの背
使い方: 食材を押し潰すようにこする
向いている食材: にんにく・しょうが
注意点: 少量向き。まな板の上で行うと安全
⚡ ミキサー/フードプロセッサー
使い方: 一口大に切った食材を数秒ミックス
向いている食材: 大根・りんご・山芋
注意点: 回しすぎると液状になるため、短時間で止める
🌀 すり鉢+すりこぎ
使い方: 円を描くようにすりつぶす
向いている食材: 山芋・しょうが・ごま
注意点: 洗う前に水をかけてこびりつきを防ぐ
💡まとめポイント
- 「叩く」タイプ → 繊維の多い野菜向き
- 「削る・こする」タイプ → 果物や柔らかい野菜向き
- 「潰す」タイプ → にんにくやしょうがなどの少量薬味に最適
食材別!代用品を使ったおろし方テク

食材ごとに適した代用方法を選ぶと、仕上がりがぐっと違ってきます。
大根は水分が多いので叩くより軽く押すのが◎。山芋は粘りを出すために滑らせるように。
にんじんやりんごはピーラーで薄く削ってから刻むと自然な口当たりになります。
それぞれの食材に合わせた“代用すりおろしテク”を覚えておけば、調理中のピンチも怖くありません。
大根・山芋 — 水分多め食材のコツ
ビニール袋+麺棒で軽く潰すと、自然なとろみが出ます。さらに、袋の中に少量の水やレモン汁を加えると酸化を防げて、色味もきれいに保てます。
山芋の場合は、粘りが強いので潰す前に皮をむいて、薄く輪切りにしてから叩くと扱いやすくなります。大根は水分を逃がさないように、袋の端を軽く閉じて空気を抜いてから潰すのがポイント。
こうすることで、余計な水分が出すぎず、シャキッとした食感が残ります。また、冷蔵庫で少し冷やしてからおろすと手が滑りにくく、仕上がりもなめらかに。
ビニール袋を二重にすると破れにくく衛生的なのでおすすめです。
しょうが・にんにく — 香りを引き出すすり方
フォークやスプーンの背で押し潰すようにすると、香りがしっかり出ます。
さらに、潰した後に数分ほど置くことで辛味成分が空気と反応し、より豊かな風味が広がります。にんにくの場合は、芯を取り除いてから潰すとえぐみが減り、香りがまろやかに。
しょうがは皮付きのまま潰すと香りが強く、皮をむいてからだとすっきりした味に仕上がります。ラップの上から押すと手が汚れず衛生的で、におい移りも防げます。
加熱料理に使うときは、潰してからすぐに炒めると香ばしさがアップ。冷奴やお刺身などの薬味として使う場合は、少し粗めに潰して食感を残すのがおすすめです。
こうしたちょっとした工夫で、しょうがとにんにくの持つ香りと風味を最大限に引き出せます。
りんご・にんじん — フルーツ系・固め食材の工夫
ピーラーで削ってから包丁で細かく刻むと、口当たりがやさしい仕上がりに。さらに、削った後に軽く塩をふって数分おくと水分が抜け、甘みが凝縮してより深い味わいになります。
りんごの場合は、少しレモン汁を加えると変色を防ぎ、見た目もきれいに仕上がります。にんじんは皮をむいた後、ピーラーでリボン状にしてから細かく刻むと、柔らかくなってお子さんにも食べやすい食感に。
サラダやドレッシングに混ぜると彩りも良く、自然な甘みが引き立ちます。固めの食材は一度に削ろうとせず、少しずつ角度を変えて削ると手が疲れにくく安全です。
最後に、削りかすもスープや炒め物に入れれば無駄なく使えて栄養満点です。
チーズ・じゃがいも — 洋食系のアレンジ利用
ミキサーを数秒だけ回すと、グラタンやハッシュポテトにも応用できます。さらに、じゃがいもは加熱してから潰すとデンプンが粘りを持ち、クリーミーな食感になります。
ミキサーにかける前に一度冷ますと、過熱によるベタつきを防ぐことができます。チーズの場合は冷凍庫で5分ほど冷やしてからミキサーにかけると、粉チーズのように細かく削れてトッピングにも便利。
少し粗めに仕上げれば、グラタンやグリル料理に加えるだけでコクと香りがアップします。また、ミキサーを長く回しすぎると油分が出てベタつくので、数秒ごとに止めながら様子を見るのがコツ。
じゃがいもとチーズを一緒にミックスしてポテトグラタンにするなど、洋食アレンジの幅も広がります。
代用品を使うときの安全・衛生チェック

おろし金の代用品を使うときに一番注意したいのは「安全」と「衛生」です。包丁やラップの刃は思った以上に鋭く、指を切る事故も少なくありません。
使用前にまな板を安定させたり、布巾を敷いたりして滑りを防ぎましょう。
また、生の山芋や大根を扱う際は、手袋をしてかぶれ防止を。使用後は、雑菌やカビを防ぐため、すぐに洗って乾かすのが鉄則です。
刃物・金属使用時のけが防止策
手元が滑りやすいときは、布巾やゴムマットで固定します。さらに、まな板の下に濡らした布巾を敷くことでズレを防ぎ、安全性がぐっと高まります。
包丁やピーラーなどを使うときは、刃の向きを常に一定にし、力を入れすぎないことがポイント。金属製の器具を使う場合は、手袋や滑り止め付きの軍手をつけると安心です。
また、刃先を下に向けて置く、使用後はすぐに水気を拭き取るなど、片づけの段階でもケガ防止の意識を忘れずに。小さな注意の積み重ねが、大きな事故を防ぐ一番のコツです。
雑菌を防ぐ洗い方&消毒のコツ
使用後すぐに熱湯消毒を行い、水分をしっかり拭き取ること。さらに、洗う前にまず食材の残りをキッチンペーパーで拭き取っておくと汚れが落ちやすくなります。
洗剤を使う場合は、刺激の少ない中性洗剤を選び、スポンジで丁寧にこすりましょう。その後、熱湯をかけて殺菌したら、風通しの良い場所でしっかり乾燥させます。
水気が残るとカビや菌の繁殖の原因になるため、布巾で拭いたあとに自然乾燥するのがおすすめです。定期的にアルコールスプレーや重曹を使うと、さらに衛生的に保てます。
特に夏場や湿気の多い季節は、使ったその日のうちに完全乾燥を心がけると安心です。
すりおろした後の保存・酸化対策
空気に触れないようラップで密封し、冷蔵なら1日・冷凍なら1週間が目安です。さらに、保存容器を使う際は、食材が空気に触れないようできるだけ平らに広げて密封するのがポイント。
大根やりんごなどは酸化しやすいため、表面にレモン汁を少量ふりかけると変色を防げます。山芋やじゃがいもは冷凍する前に軽く加熱しておくと、解凍後の水分離れが少なく、風味をキープできます。
保存袋を使う場合は、空気をしっかり抜いてから密封し、日付を記入しておくと管理しやすいです。また、使うときは自然解凍よりも冷蔵庫でゆっくり解凍する方が、風味と食感が保たれます。
食材によっては冷凍より冷蔵が向く場合もあるため、使う目的に合わせて保存方法を変えるとより長く美味しく楽しめます。
おろし金を買い換えるなら?おすすめ3選
「やっぱり専用のおろし金が欲しい」という方のために、価格帯別でおすすめ商品をピックアップしました。
100均でも十分使えるものから、無印良品やAmazonで高評価のものまで、用途に合わせて選べます。
日常使いなら手入れが簡単なプラスチック製がおすすめ。見た目と耐久性を重視するなら、ステンレスやセラミック製も人気です。
100均(コスパ最強)
ダイソーやセリアでは、軽くて洗いやすいおろし金が110円で手に入ります。最近では、プラスチック製の軽量タイプからステンレス製のしっかりタイプまで種類も豊富で、用途に合わせて選べるのが魅力です。
特にセリアの「すべり止め付きおろし金」は、手が疲れにくく安定して使えると人気。また、コンパクトなサイズなので収納場所にも困りません。
ダイソーでは、大根用としょうが用など異なる目の粗さを選べるものも販売されており、コスパ重視でも満足度は高め。
耐久性はやや劣るものの、日常使いには十分で、料理初心者や一人暮らしの方にもおすすめです。
100円という手軽さで試せるので、「とりあえず代用を卒業したい」という方には最適な選択肢です。
無印良品(見た目と清潔感)
白くてシンプルなデザインが人気で、どんなキッチンにも自然に馴染むのが魅力です。ステンレスやプラスチックの製品に比べて匂い移りが少なく、清潔感を保ちやすいのも特徴。
さらに、滑り止め付きの仕様で安定感があり、力を入れずにすりおろせます。無印良品らしい機能美が詰まっていて、収納しても見た目がすっきり。
食洗機対応のモデルもあり、お手入れも簡単です。毎日使うキッチンツールとして、長く愛用できるアイテムです。
Amazonベストセラー(性能重視)
レビュー評価の高いステンレス製は、細かく均一におろせてプロ感覚に仕上がります。特に、耐久性と切れ味の良さを兼ね備えたモデルが多く、長期間使っても摩耗しにくいのが特徴です。
多くのレビューでは「軽い力ですりおろせる」「おろした大根がふわふわに仕上がる」と高評価。中でも日本製の高品質ステンレスおろし金は、刃の角度や配置が工夫されており、繊維を潰さずにおろせるため風味が格段に違います。
また、ハンドル付きのタイプは持ちやすく、滑り止めゴム付きのものは安定感抜群。お手入れも簡単で、食洗機対応の製品も多く販売されています。
価格帯は1,000〜3,000円ほどで、長く使える品質を考えるとコスパは非常に高め。料理好きな方へのプレゼントにもおすすめです。
豆知識|すりおろすことで栄養や風味はどう変わる?

実は「すりおろす」という行為には、単なる調理以上の意味があります。繊維を壊すことで、食材に含まれる酵素や香り成分が活性化し、消化がよくなったり風味が強まったりするのです。
しょうがをすりおろすと辛味が増すのもその効果。にんじんやりんごをおろすと甘みが引き立つのも同じ理由です。おろし調理は、食材の力を引き出す“魔法の工程”といえます。
すりおろしで栄養吸収が上がる理由
繊維が細かくなることで、体が栄養を吸収しやすくなります。食材をすりおろすことで、表面積が増え、体内での消化・分解がスムーズになるため、ビタミンやミネラルが効率的に吸収されるのです。
特ににんじんに含まれるβカロテンやりんごのポリフェノールなどは、細かくすりおろすことで体に取り込みやすくなり、抗酸化作用も高まります。
また、すりおろし調理は消化器官への負担を減らし、胃腸が弱い人や子ども、高齢者にも優しい調理法。すりおろした食材は口当たりがなめらかで食べやすく、栄養補給にも最適です。
さらに、すりおろすことで酵素が活性化し、食材本来の香りや甘みを引き出してくれます。
つまり、すりおろすことは単なる下ごしらえではなく、健康的で体に優しい調理の第一歩なのです。
香り成分・酵素を活かすタイミング
調理の直前におろすことで、香りや栄養の損失を最小限にできます。時間が経つと空気中の酸素と反応して酵素が失活し、風味や栄養価が落ちてしまうため、できるだけ食べる直前におろすのがベスト。
特にしょうがやりんご、にんじんなどは、おろした瞬間に酵素が活性化し、香りが一気に立ち上ります。
調理前にすりおろして長時間置くと、色が変わったり香りが薄れたりすることもあるので注意。おろした後はラップをかけて冷蔵庫に一時的に入れておくと酸化を防げます。
また、冷たい状態で食べたい場合は、器を冷やしておくと香りの立ち方がゆるやかになり、まろやかで上品な風味を楽しめます。
すりおろしを使ったアレンジ料理例
にんじんおろしドレッシング、りんごソース、山芋とろろごはんなどに応用可能です。
さらに、しょうがおろしを使った温かいスープや、にんにくおろしを活かしたマリネソースなど、調味料としての活用も幅広いです。
りんごをおろしてヨーグルトに混ぜれば朝食にぴったりのデザートに変身。大根おろしは和食だけでなく、ハンバーグや魚のソースにも使えて万能です。
山芋をおろしてお好み焼きやとろろ蕎麦に使うと、ふんわりとした食感が楽しめます。また、すりおろした食材を冷凍保存しておくと、必要なときにすぐ使える便利な“時短ストック”にもなります。
少しの工夫で、普段の料理がぐっと豊かに、健康的にも美味しく仕上がります。
まとめ|“今あるもので工夫する力”が主婦の知恵!

おろし金がなくても、ちょっとした工夫で料理は楽しめます。大切なのは「ないからできない」ではなく、「あるもので工夫してみよう」という柔軟な発想です。
たとえば、ビニール袋と麺棒で大根を叩いてとろみを出したり、フォークでにんにくを潰して香りを立たせたりと、少しのアイデアで食卓はぐっと豊かになります。
日常の小さな知恵が、思いがけず新しい発見や笑顔を生むこともありますよね。さらに、代用品を使うことで片付けがラクになったり、洗い物が減ったりといった副産物も。
忙しい日々の中で、限られた時間を上手に使う工夫こそが“主婦の知恵”。今日ご紹介した代用アイテムや保存のコツを覚えておけば、急な来客や時間がない夕食づくりのときにも、焦らずスマートに対応できるはずです。
料理は道具よりも、発想と工夫が命。あなたのキッチンにも、きっとすぐに役立つヒントがたくさん隠れています。
明日のごはん作りが少し楽しくなる、そんなきっかけになれば嬉しいです。