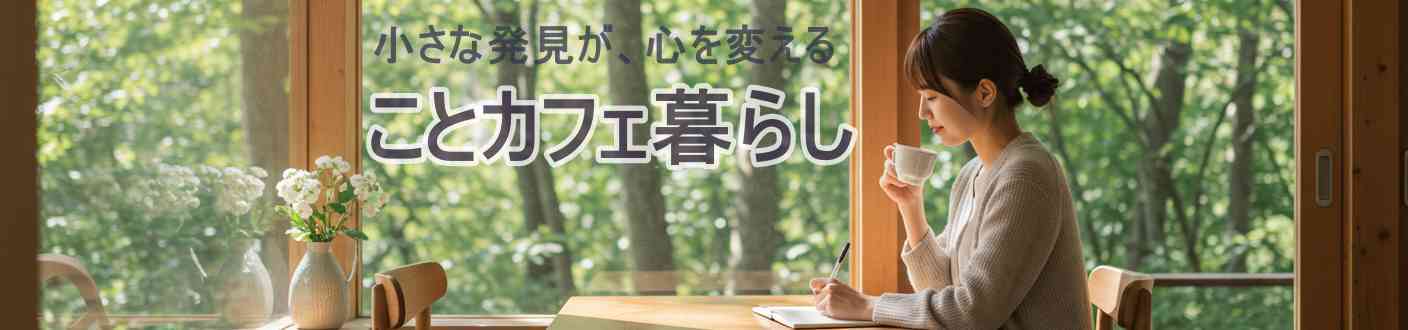新しい一年を迎えるとき、玄関に干支の置物を飾ると気持ちが引き締まりますよね。
毎年の恒例行事として楽しんでいる方も多いと思いますが、実は「いつからいつまで飾るのが正しいの?」と迷う声も少なくありません。
干支の置物には、ただの飾り以上の意味があり、飾る時期や場所、片付け方によって運気の流れが変わるとも言われています。
この記事では、風水や伝統文化の観点から、干支の置物を“より良いタイミングと方法”で飾るコツをやさしく解説します。
初めての方でも安心して実践できるよう、飾る時期・方角・処分方法・贈り方などを詳しく紹介。
「一年のはじまりを、少しでも丁寧に迎えたい」という方にぴったりの内容です。
結論|干支の置物は「立春まで」に片付けるのが一般的

干支の置物を飾る期間は、地域や家庭の習慣によって異なりますが、一般的には「立春(2月4日頃)」までに片付けるのが良いとされています。
立春は暦の上で新しい季節のはじまりであり、「旧年の気」から「新しい気」へと切り替わる節目。
このタイミングで干支を見送ることで、次の干支を気持ちよく迎える準備が整います。
「飾りっぱなし」よりも、節目で感謝を込めて片付けることで、気の流れがより整うのです。
飾る期間の目安:松の内・小正月・立春とは?
地域によっては、松の内(1月7日)までや、小正月(1月15日)までを目安にするところもあります。これらの時期はお正月行事の区切りでもあり、年神様をお見送りする意味を持ちます。
また、地域ごとの気候や生活リズムによっても違いがあり、雪深い地域では外出が難しいために少し長めに飾る家庭もあります。逆に都市部では、お正月気分が早く終わる傾向から1月7日で片付ける家庭が増えています。
松の内とは「門松を立てて年神様をお迎えしている期間」を指し、関東と関西で日程が異なるのも特徴です。小正月(1月15日)は、正月行事を締めくくる節目の日。鏡開きやどんど焼きといった行事を行うことで、年神様を送り出し、新しい日常に戻る準備をします。
立春(2月4日頃)は、暦の上で春のはじまりとされ、冬の厳しさが和らぎ始める時期。この日をもって旧年の気から新年の運気へと完全に切り替わるため、干支の置物を片付ける節目として最もふさわしいと考えられています。
干支の置物を1年飾り続けるのは縁起が悪い?
風水では「古い気を引きずる」とされるため、1年通して飾るのはおすすめされません。時間が経つにつれて、その年の干支が持つエネルギーが薄れ、停滞した気が生まれてしまうと考えられています。
また、1年中同じ置物を飾っていると、季節の変化や新しい年の運気を感じにくくなるというデメリットも。インテリアとして楽しむ場合でも、季節ごとに小物や花を変えて“新しい空気を取り入れる”ことを意識すると良いでしょう。
たとえば春には明るい花や桜モチーフを添え、夏は涼しげなガラス小物を一緒に飾るといった工夫がおすすめです。秋冬には松や干支に関連するモチーフを加えることで、年間を通して変化を楽しめます。
どうしても片付けるのが惜しい場合は、玄関以外のリビングや棚などに飾り場所を変えて、目立たない形で残すのもひとつの方法です。大切なのは、“今の年の主役を立てること”。古い干支を完全に排除する必要はなく、感謝とともに場所を譲る気持ちを持つことで、良い気の流れを保てます。
干支の置物の意味と飾る理由

干支の置物は、単なるお正月飾りではなく「その年の運を司る象徴」です。
十二支それぞれに込められた意味があり、家庭や職場の安全・繁栄・健康を願う縁起物として古くから大切にされてきました。
中でも玄関に飾ることは、「良い気を迎え入れる入り口を整える」という意味があるんです。
干支の置物が象徴する運気と意味
干支にはそれぞれテーマがあります。例えば、辰年は「上昇・発展」、巳年は「財運・再生」、午年は「情熱と成功」など。自分や家族の願いに合わせた干支を意識して飾ると、気持ちにも前向きな変化が生まれます。
また、子年は「繁栄と始まり」、丑年は「忍耐と努力」、寅年は「挑戦と守護」、卯年は「飛躍と調和」、未年は「安定と優しさ」、申年は「知恵と発展」、酉年は「成功と実り」、戌年は「誠実と守護」、亥年は「勇気と前進」を象徴します。それぞれの干支が持つ意味を知ることで、自分の願いや人生のテーマに合った飾り方が見つかります。
例えば、仕事運を高めたい人は辰や酉を、家庭運を整えたい人は未や戌を選ぶとよいとされます。干支の持つエネルギーは“その年だけでなく、自分に必要な運気を呼び込むお守り”としても働きます。
さらに、素材や色によっても象徴する意味が変わります。金色の置物は金運、白色は浄化、木製は安定、陶器は安心感をもたらすとされます。こうした小さな工夫を取り入れることで、干支の置物は単なる飾りではなく、毎日の暮らしに寄り添う心の支えとなるのです。
玄関に飾ることで得られる風水的効果
風水では、玄関を“気の入り口”と考えます。そこに干支を飾ることで、幸運を呼び込み、悪い気を防ぐ効果が期待できます。特に明るく清潔な玄関に置くことで、エネルギーの流れがスムーズになります。
さらに、玄関は家族全員の運気の通り道でもあります。玄関の状態が整っていればいるほど、良い気がスムーズに入り込み、家全体の雰囲気も軽やかに変わります。干支の置物を飾ることで、外から帰ってきたときにポジティブな気を呼び戻す“リセットの場”を作ることができるのです。
また、風水的には干支の置物の素材や色も重要とされています。陶器は「安定」、木製は「成長」、金属は「繁栄」、ガラスは「浄化」を意味します。白や金などの明るい色合いの置物を選ぶと、空間全体が浄化され、より清らかな印象になります。
もし玄関が狭い、または日当たりが悪い場合は、小さな観葉植物や明るい照明を添えてあげましょう。植物は気を循環させ、照明は陽の気を呼び込みます。干支の置物と組み合わせることで、“家の入り口”が心地よいエネルギーに満ちた空間へと変わります。
各干支の特徴と願いが込められた意味
例えば、子(ねずみ)は繁栄、丑(うし)は忍耐、寅(とら)は勇気。卯(うさぎ)は調和と飛躍、辰(たつ)は上昇と守護、巳(へび)は再生と財運、午(うま)は情熱と自由、未(ひつじ)は穏やかさと家庭運、申(さる)は知恵と柔軟性、酉(とり)は実りと成功、戌(いぬ)は忠誠と安心、亥(いのしし)は勇気と前進を象徴します。
こうした特徴を意識して飾ることで、自分や家族が迎える一年への願いをより明確にすることができます。また、その年の干支の意味を知ることで、目標や行動のヒントが得られることもあります。例えば、寅年には「挑戦する勇気を大切にする」、未年には「家族との絆を深める」といった形で、日常のテーマづくりにも役立ちます。
さらに、干支の置物を通じて日本の暦文化や自然観にも触れられます。古くから干支は農作業や季節の節目を示す目印でもあり、ただの動物ではなく“時の流れ”を象徴する存在でした。干支ごとの意味を感じながら飾ることで、一年をより丁寧に過ごそうという気持ちが自然と生まれ、飾り物に込められた祈りの力を感じ取ることができるでしょう。
玄関に飾るときの基本ルールと方角

干支の置物を飾る場所選びは、実はとても大切です。風水の考え方では、置く位置や高さ、向きによって「気の流れ」が変わるとされます。
清潔で明るい場所、目線より少し高い位置に置くのが理想です。
置き場所・高さ・向きの選び方
干支の置物は玄関の正面ではなく、少し右側か左側にずらして置くのがベスト。
また、外に向けるよりも“家の中を守るように内向き”に飾ると良いとされています。
さらに、置く高さにもポイントがあります。目線より少し高い位置、もしくは胸の高さに飾ることで、置物に対して自然に視線が向き、気の流れがスムーズになるといわれています。低すぎる場所は運気が下がりやすく、逆に高すぎると気が散ってしまうため、ほどよい高さを意識しましょう。
方角については、その年の干支の“吉方位”を意識するのもおすすめです。例えば辰年や巳年なら東南、寅年や卯年なら東が良いとされるなど、干支ごとに縁起の良い方向が存在します。家全体の間取りや日当たりも考慮しながら、明るく清潔な位置を選びましょう。
また、置物の周囲にスペースを少し空けてあげることで、気の流れが停滞せずに循環しやすくなります。できれば下に白い布や木の台座を敷き、“清めの土台”を作るとさらに運気がアップします。
ちょっとした工夫で、玄関が心地よいエネルギーに満ちた空間に変わるでしょう。
避けるべき場所(ドア近く・下駄箱の上など)
ドア付近は風の通りが強く、気が安定しにくい場所。出入りのたびに空気の流れが変わるため、せっかくの良い気が外に逃げてしまうこともあります。また、人の動きが多い位置に置くと、置物がぶつかったり落ちたりして運気が乱れる原因にもなります。
下駄箱の上は埃が溜まりやすく、湿気もこもりやすい場所。靴のにおいや汚れが気の流れを濁らせるため、干支の置物を飾るにはあまり適していません。
もしどうしてもその場所に飾りたい場合は、白い布を敷いたり、定期的に掃除をして清潔な状態を保つことが大切です。
また、トイレや浴室の近くも避けましょう。これらの場所は陰の気が強く、干支の置物が持つ“陽の気”を弱めてしまうことがあります。できるだけ明るく乾燥したスペースを選ぶことが、風水的にも開運につながります。
理想は、家族が出入りするときに目に入りやすい、静かで安定した場所。そこに飾ることで、毎日の挨拶のように自然と干支のエネルギーに触れ、穏やかな気持ちで過ごせるでしょう。
清潔に保つことで気の流れを良くする方法
定期的に乾いた布で拭いたり、花や明かりを添えると気の巡りがよくなります。
「飾る=整える」という意識が運を呼ぶポイントです。
さらに、掃除のタイミングも重要です。朝の光が差し込む時間帯に軽く拭くと、陽の気を取り込みやすくなり、一日を明るい気分でスタートできます。特に年末や季節の変わり目など、空気が入れ替わる時期に掃除をすると、停滞した気をリセットできるでしょう。
また、花や明かりを添えるときは、季節感を意識するとより良い効果が得られます。春は桜やチューリップ、夏はひまわりや緑の葉物、秋は紅葉やすすき、冬は松や南天などを組み合わせて飾ると、自然のエネルギーを取り入れることができます。照明は暖色系の柔らかい光を選ぶと、玄関全体に温かみが生まれ、訪れる人にも安心感を与えます。
さらに、香りを取り入れるのもおすすめです。お香やアロマを軽く焚くと、空気が浄化され、干支の置物の持つ陽の気が引き立ちます。
大切なのは「汚れを落とす」というよりも、「空間を整える」という気持ち。毎日の小さな習慣が、心の余裕と運の流れをつくってくれるのです。
干支の置物を飾る時期と飾り始めのマナー

「いつまで?」だけでなく「いつから飾るか」も大切なポイントです。
運気を呼び込むためには、良い気が巡るタイミングでスタートすることが大切。
飾り始めは「大掃除後~元旦前」が理想
掃除を終えたあと、玄関を清めてから飾るのが基本です。大晦日にバタバタと出すよりも、心に余裕のある28日頃までに準備をすると良いでしょう。
さらに理想的なのは、掃除の際に“感謝の気持ち”を込めながら清めること。古い埃や汚れを落とすことで、昨年の停滞した気が浄化され、新しい年の運気が入りやすくなります。清めの塩やお香を使うと、より神聖な空気に整えることができます。
飾る際は、干支の置物を両手で丁寧に扱い、「今年もよろしくお願いします」と声に出して飾ると気持ちが安定します。また、28日を過ぎてしまった場合でも焦らず、29日は「苦の日」と言われるため避け、30日や31日よりも前に準備するのが理想です。
干支の置物を飾る行為は、単なる準備ではなく“心を整える儀式”のようなもの。掃除を終えた清々しい空気の中で飾ることで、気持ちも前向きになり、新しい一年を迎える心の準備が自然と整います。
避けたほうがよい日(仏滅など)はある?
絶対ではありませんが、気持ち的に避けたい方は「大安」「先勝」などを選ぶと安心です。
日本では古くから“六曜”という暦の考え方があり、仏滅・大安・先勝・友引などの日を意識して行動を決める風習があります。
飾る日もこれに合わせると、より気持ちが整いやすくなります。特に仏滅は「物事のスタートに向かない」とされるため、気になる方は避けたほうが無難です。
反対に「大安」はすべてにおいて吉、「先勝」は午前中に縁起が良い日とされているため、飾る時間帯を工夫するのもおすすめです。たとえば、午前中の明るい時間に飾ることで陽の気を取り込み、家全体の雰囲気が明るくなる効果が期待できます。
とはいえ、六曜にとらわれすぎず、自分や家族の気持ちが穏やかで前向きな日に飾ることが何より大切。気持ちの状態がそのまま“気の流れ”に反映されるため、「今日は新しい気を迎えたい」と思えたタイミングを選ぶのが一番の吉日と言えるでしょう。
風水的に運気が上がる「飾り始め日」
冬至明けや大安など、“新しい光が入る日”が開運日とされています。そのタイミングで玄関に飾ると、よりポジティブなエネルギーを迎えられます。
風水では、太陽の力や自然のエネルギーが最も高まるタイミングを重視します。特に冬至は「陰から陽へと転じる日」とされ、古くから“再生”や“スタート”の象徴と考えられてきました。冬至を過ぎると日が少しずつ長くなり、光のエネルギーが増えていくため、物事を始めるには最適なタイミングとされています。
また、二十四節気で見ると「小寒」「大寒」など寒さが厳しい時期を経て、「立春」へと向かう流れは、運気の変化を象徴する期間です。この間に干支の置物を飾ることで、冬の静かな気を浄化し、新たな春のエネルギーを先取りすることができます。
さらに、日柄では「一粒万倍日」や「天赦日」もおすすめです。一粒万倍日は“始めたことが何倍にも実る日”とされ、天赦日は“すべての神々が天を開いて許す日”と呼ばれる最上吉日。こうした日を選んで飾ると、運気の流れがよりスムーズになります。
もちろん、特別な日を逃しても大丈夫です。大切なのは“心が落ち着いている時”に飾ること。焦らず自分にとって心地よいタイミングで飾れば、その気持ちが良いエネルギーとして空間に伝わり、自然と運を呼び込むでしょう。
地域や宗派によって異なる飾り方の違い

干支の置物の飾り方や片付け時期には、地域や宗派による違いがあります。どちらが正しいというより、「自分の家に合うやり方」を選ぶことが大切です。
関東と関西で違う“松の内”の期間
関東では1月7日まで、関西では1月15日までが松の内。これに合わせて干支の置物を片付ける家庭も多いです。
この違いは、江戸時代に遡る文化的背景に由来しています。江戸を中心に発展した関東では、幕府が「七日までを松の内」と定めたため、早めに正月飾りを片付ける習慣が広まりました。
一方で、京都や大阪を中心とする関西では、旧暦の名残を重んじて十五日までを松の内とする風習が続いています。
そのため、関東出身の方が関西で生活する場合や、その逆では「どちらに合わせるのが良いの?」と迷うこともあるでしょう。基本的には、現在住んでいる地域の慣習に合わせるのが自然です。
地域の神社やお寺では、その土地ごとの行事スケジュールに合わせて神様をお見送りするため、地元に合わせることで気の流れが整いやすくなります。
また、現代ではライフスタイルの変化により、共働き世帯や都市部では7日までに飾りを片付けるのが難しいケースも増えています。その場合は、小正月(15日)や次の週末まで延ばしても問題ありません。大切なのは「だらだらと出しっぱなしにしない」こと。
節目を意識して気持ちを切り替えることが、干支の置物を通して良い運気を保つ秘訣です。
神道と仏教での扱いの違い
神道では「年神様を迎える縁起物」として考えられ、家や家族を守る神様に対して敬意を表す意味があります。新年に干支の置物を飾ることは、年神様を迎えるための清らかな準備であり、“神聖な空間を整える行為”とされています。
特に玄関や神棚など、神様が出入りするとされる場所に置くことで、福を呼び込みやすくなると考えられています。
一方、仏教では干支の置物を「感謝と供養の象徴」として扱うこともあります。過ぎ去った年への感謝や、亡くなった方への祈りを込めて飾ることで、心を静め、穏やかな気持ちで新しい一年を迎える準備をするという意味合いがあります。寺院によっては、干支にちなんだ守り本尊やお守りを授与するところもあり、仏教的な側面からも一年の幸福を祈る風習が続いています。
このように、神道では“迎える”、仏教では“祈る”というように、干支の置物に込める意味合いが少し異なります。
しかし、どちらの考え方にも共通しているのは「感謝」と「調和」の心。信仰や宗派の違いにとらわれず、干支の置物を通して自分や家族の幸せを願う気持ちを大切にすることが、最も自然で美しい形と言えるでしょう。
地方の伝統行事と干支飾りの関係
雪国などでは旧暦に合わせて長く飾る習慣もあります。寒さが厳しく外出が難しい地域では、春の訪れをゆっくりと感じながら飾り続けることで、一年の無事と豊穣を願う意味が込められています。
また、地域によっては「どんど焼き」や「左義長(さぎちょう)」などの火祭り行事と一緒に干支飾りを片付ける風習もあります。これらの行事は、正月に迎えた年神様を炎とともに天へ送り返す意味を持ち、干支の置物やしめ縄を一緒に供養することで、感謝の気持ちを伝える儀式となっています。
南の地域では、旧暦の正月(2月頃)に再び飾り直す文化も残っています。これは“春の節目”を重んじる風習で、地域の自然サイクルと密接に関係しています。
特に農村部では、干支の置物を田の神や家の守り神と結びつけ、農作物の実りや家族の健康を祈る象徴として扱うこともあります。
このように、干支飾りの扱いは地域の風土・気候・生活リズムと深く結びついており、「いつまで飾るか」というルールよりも、その土地で大切にされてきた“心のタイミング”を尊重することが一番自然です。
干支の置物を「贈る」時のマナーと意味

年末になると、干支の置物をプレゼントに選ぶ方も増えます。ですが、贈る相手やタイミングによっては注意が必要。ここでは、贈り物としてのマナーや選び方を紹介します。
目上の方に贈るときの注意点
陶器製や木製の落ち着いたデザインを選ぶと好印象です。派手すぎるものや奇抜なデザインは控え、上品で品格のあるものを選びましょう。色合いも、白・ベージュ・金など落ち着いたトーンがおすすめです。
特に目上の方や上司へ贈る場合は、相手の家の雰囲気や好みに合わせることも大切です。あまりにも大きすぎるものや存在感が強すぎるものは、相手に気を遣わせてしまうことがあります。飾りやすいサイズ感や、控えめなデザインを意識すると良い印象を与えます。
また、メッセージカードや一言添える場合は、「新しい一年が実りあるものになりますように」「お健やかにお過ごしください」など、季節の挨拶とともに感謝の気持ちを込めましょう。包装紙はシンプルで清潔感のあるものを選び、紅白のリボンや水引を加えると華やかさが増します。
贈り物は“気持ち”を伝えるものです。値段よりも心のこもった選び方や渡し方が、最も印象に残るポイントになります。
避けたほうが良い干支モチーフ
相手の干支とかぶるデザインや、過度に金ピカなものは避けるのが無難です。特に、相手の生まれ年と同じ干支を贈ると「自分の気を上書きする」と考えられる地域もあり、避けた方が安心です。また、派手すぎる金色や原色を多用したデザインは風水的に“気が強すぎる”とされ、かえって落ち着かない印象を与えることもあります。
さらに注意したいのは、素材や形の印象です。たとえばガラス製や金属製の置物はスタイリッシュですが、冷たさを感じやすいため、温かみを重視する相手には不向きです。逆に木製や陶器の柔らかい質感は安心感を与え、誰にでも好まれやすいでしょう。
また、キャラクター風やコミカルすぎるデザインは、親しい友人には喜ばれても目上の方や取引先にはカジュアルすぎる印象になります。相手の性格や飾る場所(玄関・リビング・オフィスなど)を想像して、シーンに合った上品なテイストを意識することが大切です。
縁起が良い素材(陶器・木製・金属)と選び方
陶器は「安定」、木製は「成長」、金属は「繁栄」を象徴します。贈る相手の性格や願いに合わせて選ぶと、気持ちが伝わります。
陶器の置物は、土のエネルギーを宿すとされ、どっしりとした安定感をもたらします。特に家庭運や健康運を整えたい人への贈り物にぴったりです。艶のある釉薬が施された陶器は、高級感がありながらも温かみを感じさせるため、目上の方にも喜ばれやすいでしょう。
木製の置物は、生命力や成長の象徴です。木のぬくもりが優しく、家庭や人間関係の調和を願う意味合いを持ちます。ヒノキや桜など、日本ならではの木材を使ったものは香りも良く、飾るだけで空間に柔らかいエネルギーをもたらします。新築祝いや出産祝いなど、“新しいスタート”を迎える人への贈り物にも最適です。
金属製の置物は、輝きと強さを象徴します。金運や仕事運を高めたい人におすすめで、ステンレスや真鍮など素材によって印象が変わります。シルバー系は知的でクール、ゴールド系は華やかで力強い印象を与えます。
選ぶときのポイントは、相手が“どんな一年を過ごしたいか”をイメージすること。たとえば、挑戦の年にしたいなら金属製、落ち着きを求めるなら陶器製、家族の絆を深めたいなら木製といった具合に、想いを込めて選ぶとより心に響く贈り物になります。
片付けと処分の正しい方法

干支の置物を片付けるときは、「ありがとう」の気持ちを込めることが大切です。扱い方ひとつで、その年の締めくくりが穏やかになります。
お焚き上げ・神社への納め方
感謝を伝えて神社でお焚き上げをしてもらうのが一番丁寧な方法です。近くの神社では「古札納め所」に出せる場合もあります。
より丁寧に行いたい場合は、紙袋に入れる前に白い紙で包み、軽くお清めの塩をふると良いとされています。これは、長い間家を守ってくれた置物に対して「ありがとうございました」という感謝の意を示す意味があります。直接神社へ持参できない場合は、年末年始に行われる「古神札焚上祭」などの行事に合わせて納めるのもおすすめです。
また、地域によっては「どんど焼き」や「左義長」と呼ばれる火祭りで、しめ縄やお守りと一緒に干支の置物を焼いて感謝を伝える風習もあります。こうした儀式では、炎を通して“新しい年への希望”を天に届けるとされています。
遠方に住んでいて持ち込みが難しい場合は、郵送でお焚き上げを受け付けている神社もあります。その際は、メッセージカードや「感謝」と書いた紙を添えると丁寧です。いずれの方法でも大切なのは、物としてではなく“心を込めて見送る”意識を持つこと。干支の置物を通して、今年一年の感謝と新しい年への祈りを静かに伝えましょう。
保管・再利用はOK?
お気に入りの干支は、箱に入れて丁寧に保管してもOKです。長年愛着のある置物は、思い出や家族の絆を感じさせる大切な存在でもあります。保管する際は、埃や湿気を防ぐために柔らかい布で包み、風通しの良い場所にしまうと良いでしょう。紙や新聞紙ではなく、通気性のある和紙や布袋などを使うと劣化を防げます。
また、数年に一度取り出して軽く拭き、日光に当てずに陰干しすることで、気の流れをリフレッシュできます。再利用する場合は、前年の干支を「ありがとう」と声をかけてから、新しい年の置物と一緒に飾るのもおすすめ。古い干支を脇役として飾ることで、“過去の運気と現在の運気をつなぐ橋渡し”のような意味を持たせられます。
ただし、次の年には新しい干支を主役にするのを忘れずに。主役交代の意識を持つことで、家の中の気が切り替わり、流れが停滞せずにスムーズになります。思い出を大切にしつつ、新しい年を迎える準備を丁寧に行うことが、より良い運を呼び込む秘訣です。
家庭ゴミで捨てる際の注意点
燃えるゴミとして出す場合も、紙に包んで「今までありがとう」と言葉をかけてから処分すると気持ちが整います。さらに、白い紙や半紙など清潔な素材で包み、できるだけほかのゴミと分けて出すようにしましょう。これは“感謝を込めて見送る”という気持ちを形にする大切なステップです。
可能であれば、処分する前に軽く拭いて汚れを落とし、数秒間でも手を合わせて心の中でお礼を伝えると、心の整理にもつながります。神聖な意味を持つものだからこそ、最後まで丁寧に扱う姿勢が大切です。
また、自治体によっては陶器や金属製の干支飾りを燃えないゴミとして分別する必要がある場合もあります。素材を確認し、分別ルールを守ることも“気を整える”行動のひとつ。正しい方法で手放すことで、空間に新しいエネルギーが入りやすくなり、次の年の運気もスムーズに流れ始めます。
新しい干支の置物を迎える準備

新しい干支を迎えるときは、「古いものを整えて、新しい気を入れる」ことがポイントです。
飾り始めはいつがベスト?(大掃除後・元旦)
大掃除で玄関を清めたあと、元旦に合わせて新しい干支を飾ると、運気が入りやすくなります。さらに理想的なのは、12月28日頃までに大掃除を済ませ、清めた空間に穏やかな気持ちで新しい干支を迎えることです。慌ただしい大晦日や年明け直前ではなく、少し余裕を持って飾ることで、落ち着いた“気”が流れやすくなります。
飾る時間帯は、朝の光が入る時間がおすすめ。太陽のエネルギーが満ちる午前中に飾ると、陽の気が家全体に広がりやすく、気持ちも自然と前向きになります。夜に飾る場合は、柔らかな照明を灯しながら、静かな気持ちで「今年もよろしくお願いします」と声をかけると良いでしょう。
また、飾る際には干支の置物を両手で包み込むように持ち、優しく扱うことが大切です。風水では“ものに心が宿る”と考えられており、丁寧に扱うことでその年の運気がより穏やかに整うとされています。さらに、家族がそろって飾ることで、家庭内の調和も深まり、良いスタートを切ることができます。
このように、飾り始めのタイミングや所作を丁寧に行うことで、干支の置物は単なる正月飾りではなく、“一年の幸せを招く最初の儀式”としてより深い意味を持つようになります。
飾る前に行いたい玄関の清め方
塩水で軽く拭いたり、盛り塩を置くのも良い方法です。香りのよいお花やキャンドルを添えるのも◎。さらに、玄関の床やドアノブ、取っ手など人の手がよく触れる部分も丁寧に拭き上げると、目に見えない“気の汚れ”までスッキリと浄化されます。
清めに使う塩水は、天然塩を使うのが理想です。水に少量の塩を溶かし、柔らかい布で軽く拭くだけでOK。特に玄関の敷居や扉の内側は、外から入る気を和らげてくれる場所なので重点的に行うと良いでしょう。盛り塩を置く際は、玄関の両端や人の目線より下の位置に置くのが風水的にベストです。
また、香りの演出も重要です。お花を飾る場合は、白い花やグリーン系の植物が浄化効果を高めます。キャンドルを灯す場合は、オレンジやシトラスなどの香りを選ぶと“陽の気”を呼び込みやすくなります。夜は火の代わりにディフューザーを使うのも安心です。
玄関を清める行為は、単なる掃除ではなく“運気の扉を開く準備”でもあります。明るく清らかな玄関に整えることで、干支の置物のエネルギーがより調和し、家全体に優しい流れを生み出します。
旧年の置物を感謝とともに見送る
片付ける際は、「一年ありがとう」という気持ちを込めましょう。丁寧に扱うことで、次の年も良い気が流れます。さらに、片付けるときは急がず、一つひとつの動作を落ち着いて行うのがポイントです。柔らかい布で軽く拭き、ほこりを取り除きながら「この一年を守ってくれてありがとう」と声をかけてあげると、気持ちの整理にもなります。
また、干支の置物を包む際には白い布や和紙など清潔な素材を使い、箱にしまう前に少量の塩を添えると、お清めの意味が加わります。特に陶器や木製の置物は年月を重ねるほど“家の気”を吸っているとされるため、感謝を込めて休ませることが大切です。
さらに、家族で一緒に片付けるのもおすすめ。子どもや家族に「この干支はこういう意味があるんだよ」と伝えながら見送ると、風習の継承にもつながります。こうして感謝を形にして締めくくることで、家全体の空気がリセットされ、次の干支を迎える準備が自然と整うのです。
干支の置物と相性の良いインテリア・色使い

玄関の印象は家全体の“運気の顔”です。干支の置物に合った色や素材を取り入れることで、開運効果をより高めることができます。
玄関インテリアに馴染む色・素材
木の温もりや白を基調にした空間は、どんな干支にも合います。自然素材の台座や小物を添えると統一感が出ます。さらに、木目や石目など自然素材の質感を活かすことで、干支の置物が持つ“生命力”や“安定感”をより引き立てることができます。たとえば、木製の台座の上に陶器の干支を置くと、土と木のエネルギーが調和し、家庭運を高めるといわれています。
また、照明とのバランスも重要です。白やベージュを基調とした空間には、暖かみのある間接照明を合わせると、干支の置物の陰影が柔らかく浮かび上がり、優しい印象を演出できます。逆にモダンな玄関には、シルバーやグレーの金属素材を少し取り入れることで、清潔感とスタイリッシュさを両立できます。
加えて、玄関マットや壁飾りなども干支の雰囲気に合わせると、空間全体に一体感が生まれます。干支の色に合わせた小物をさりげなく配置するだけでも、風水的な調和が取れ、訪れる人に心地よさを感じさせるでしょう。
運気を呼び込む配色(例:金・白・グリーン)
金は豊かさ、白は浄化、グリーンは成長を意味します。アクセントとして取り入れると運気が上がりやすいです。さらに、風水的にはこの3色の組み合わせがバランスを整える役割を果たすといわれています。金色は金運や仕事運を引き上げ、白は空間を清めて悪い気をリセットし、グリーンは人間関係や健康運を安定させるとされています。
この3色を同時に取り入れる場合は、全体のバランスを意識することがポイント。金をアクセントにし、白をベースに、グリーンを小物で添えると自然で上品な印象になります。例えば、白い玄関マットに金の縁取りがあるものを選び、横に小さな観葉植物を置くだけでも気の流れが穏やかに整います。
また、季節ごとの彩りを加えるのもおすすめです。春は明るいグリーンを、夏は爽やかな白を、秋は落ち着いたゴールドを、冬は柔らかなベージュやアイボリーを取り入れると、年間を通じて運気のバランスが維持しやすくなります。配色は単なるインテリアの美しさだけでなく、日々の気分や家族の調和にも影響を与える大切な要素なのです。
避けたい色の組み合わせとは?
黒と赤を多用しすぎると気が乱れやすいとされます。落ち着きと明るさのバランスを意識しましょう。さらに、風水の観点では黒は「陰の気」、赤は「強い陽の気」を象徴し、この2色を過度に組み合わせるとエネルギーがぶつかり合って不安定になるといわれています。特に狭い玄関や暗い空間でこの配色を使うと、圧迫感や緊張感を感じやすくなり、家全体の気が落ち着きにくくなります。
とはいえ、完全に避ける必要はありません。黒をベースにする場合は、ベージュや白を差し色として取り入れると全体が柔らかくなります。赤を使いたい場合は、小物や花などの“ワンポイント”で加えるとエネルギーのアクセントになり、活気をプラスしてくれます。
また、干支の置物が金色や白など明るい色合いの場合、背景を落ち着いたグレーやナチュラルウッドにすることで調和が取れ、上品で温かみのある空間を作ることができます。重要なのは、“色同士を喧嘩させない”こと。目に優しいトーンの組み合わせを意識すれば、穏やかで心地よい玄関になります。
干支の置物を毎年飾る意味と“バトンタッチ”の考え方
毎年の干支を大切に飾ることは、「年ごとのエネルギーを受け取り続ける」という意味があります。前年の干支とのつながりを意識することで、より豊かな時間が流れます。
前年の干支を残してもOKなケース
玄関以外の棚やリビングの一角に飾るなら問題ありません。ただし“主役は新年の干支”を意識しましょう。さらに、前年の干支を残すことで、その年に積み重ねてきた努力や経験を“継続するエネルギー”として引き継ぐことができるとも言われています。たとえば、前年の干支をリビングの北側や書斎など落ち着いた空間に置くと、学びや忍耐、安定を象徴する力が保たれやすくなります。
また、前年の干支を飾る際には、新年の干支と向かい合わせるのではなく、少し角度をずらして“お互いを見守るように”配置するのがポイントです。これにより、両者の気が衝突せず、自然に流れるようになります。干支同士を上下で飾る場合は、古い干支を下、新しい干支を上にすることで、時の流れを象徴的に表現できます。
さらに、インテリアとして調和させるために、前年の干支には落ち着いた色合いの台座や小物を合わせ、新しい干支には明るいトーンを取り入れると、自然と主役交代の印象が生まれます。こうした小さな工夫が、家庭内の気の循環をスムーズにし、前向きな流れを育ててくれるのです。
2体並べる場合の風水的な考え方
前後に並べて「バトンを渡す」ように配置すると、良い気が流れます。さらに、干支の交代を象徴するこの配置は、“過去から未来への流れ”を表すとされ、家庭や仕事における運気の循環をスムーズにしてくれる効果があるといわれています。
前に置く新しい干支は“これからのエネルギー”を司り、後ろに置く前年の干支は“今までの努力と経験”を支える存在です。そのため、前後の距離を少し空けて配置すると、気の流れが自然に生まれ、両方の力がうまく調和します。間に小さな観葉植物やキャンドルなどを添えると、“橋渡し”の象徴になり、より優しい気の循環を促します。
また、左右に並べる場合は、新年の干支を右(陽)、旧年の干支を左(陰)に置くと風水的なバランスが取れやすくなります。この並びは、東から昇る朝日が右側を照らす流れと同調し、“新しいスタート”を後押しする配置とされています。
飾る際は、ただ並べるだけでなく「今年もよろしくね」「お疲れさま」と心の中で言葉をかけることも大切です。そうした気持ちのやり取りが空間に穏やかな波動を生み出し、家全体のエネルギーを温かく包み込んでくれるでしょう。
世代を超えて受け継ぐ飾り方(親から子へ)
親から譲り受けた干支飾りを大切にするのも素敵です。家族の絆を象徴するインテリアとして引き継ぐことで、温かな運を呼び込みます。さらに、こうした干支飾りは“家の守り神”のような存在として、代々受け継がれていくことに意味があります。祖父母から受け取ったものを大切に飾ることで、過去と現在、そして未来をつなぐ“家の歴史”が静かに息づくのです。
飾り方にも工夫を加えると、より深い意味を持たせられます。たとえば、親から譲り受けた干支飾りを家族写真の近くに飾ると、“絆”を象徴する空間になります。特に玄関やリビングの目立つ位置に置くことで、家族全員が自然と目にするたびに“つながり”を感じることができます。
また、年ごとに新しい干支を迎える際には、古い干支と一緒に短期間だけ並べて飾るのもおすすめです。これは、“想いを引き継ぎながら新しい年を迎える”という意味合いを持ち、運気の流れを穏やかに切り替えてくれるといわれています。親から子へ、子から孫へと受け継がれる干支飾りは、単なる置物ではなく、“家族の心をつなぐ物語”として、年を重ねるほどに輝きを増していくのです。
干支の置物を活用した“年末年始の開運アクション”

干支の置物を通して、年末年始をもっと特別に過ごすアイデアを紹介します。
置物と一緒に飾ると良いアイテム(鏡餅・花・しめ縄)
鏡餅やしめ縄と並べて飾ることで、「清めと迎え入れ」の調和がよりいっそう整います。鏡餅は神様を迎える清らかさを象徴し、しめ縄は邪気を払う結界の役割を果たします。干支の置物をその中央に配置すれば、まるで神聖なステージのように空間が引き締まり、新しい一年のエネルギーを呼び込みやすくなります。
さらに、小さな花や松飾りを添えると華やかさと生命力が加わります。たとえば、南天や千両の赤い実は「難を転ずる」意味を持ち、松は永遠の繁栄を象徴します。季節の花を一輪添えるだけでも、空間の印象がぐっと明るくなり、干支の置物が持つ“守り”の力が引き立ちます。また、器や敷物に白や金を取り入れると、浄化と発展のエネルギーがより強まります。飾りの配置バランスを意識して、清らかで温かみのある正月の空間を演出しましょう。
年末の大掃除で運気をリセット
掃除をしてから飾ることで、不要な気が流れ、良い運が入りやすくなります。さらに、年末の大掃除は単なる“片付け”ではなく、1年間にたまった運気の滞りをリセットする大切な儀式です。玄関やリビング、窓際など、気の出入りが多い場所から順番に掃除すると、空間全体の流れがスムーズになります。
掃除をするときは、ほこりを払うだけでなく、“感謝”の気持ちを込めて拭くことがポイントです。例えば「今年も守ってくれてありがとう」と声をかけながら玄関を磨くと、家そのもののエネルギーが清められ、より良い運を迎え入れやすくなります。また、使用する掃除道具にも工夫を。天然素材のほうきや布を使うと、自然の力が加わり浄化効果が高まると言われています。
大掃除の仕上げには、窓を開けて新鮮な空気を取り込みましょう。風が通ることで古い気が外へ出て、新しい運がスッと入り込んできます。こうして空間を整えた後に干支の置物を飾れば、清らかで前向きなエネルギーに包まれた新年を迎えられます。
新しい一年を迎える前の「感謝の儀式」
家族で感謝の言葉を伝えながら飾ると、より深い意味を感じられます。さらに、このひとときは単なる飾り付けではなく、家族の心をひとつにする大切な時間でもあります。たとえば、一年を振り返りながら「今年も健康で過ごせたね」「みんなで頑張ったね」と言葉を交わすだけで、空間に温かなエネルギーが満ちていきます。
飾り付けの際には、家族それぞれが役割を分担するのもおすすめです。誰かが掃除をして、誰かが干支の置物を拭き、子どもが花を飾る──そんな協力の過程自体が、家族の絆を深める“感謝の儀式”となります。さらに、静かな音楽を流したり、季節の香りのするお香を焚いたりすることで、心が落ち着き、丁寧に一年を締めくくる雰囲気を演出できます。
このように、飾る行為そのものに感謝を込めることで、干支の置物は単なる縁起物を超え、“心を整える象徴”として輝きを増します。家族で共有するこの穏やかな時間が、翌年の幸運を呼び込む最初の一歩になるのです。
まとめ|干支の置物は“飾る心”で運を呼び込む

干支の置物は、ただのインテリアではなく「心の整理」と「感謝の象徴」です。飾るという行為は、空間を整えるだけでなく、自分自身の内面を整える時間でもあります。置物を選ぶ瞬間、飾る位置を考えるとき、そして片付けるとき──その一つひとつに、感謝や気づきが宿ります。だからこそ、丁寧に向き合うほどに、干支の置物は“心の鏡”のように、あなたの暮らしを美しく映し出してくれるのです。
飾る時期や片付け方、日々の手入れにはそれぞれ意味があります。時期を守って飾ることで季節の流れを感じ、丁寧に手をかけることで気の流れが整い、自然と運が巡り始めます。たとえ忙しい日々の中でも、干支の置物を通じて自分の気持ちをリセットするひとときを持つことで、心にゆとりが生まれるでしょう。
一年を通して、干支の置物を眺めるたびに、自分や家族の成長や変化を感じられるように。今年も“良い気”が玄関からすっと入り、笑顔が絶えない日々を迎えられるよう、心をこめて飾りましょう。